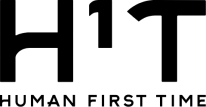健康経営とは?目的やメリット、健康経営優良法人認定制度についてわかりやすく解説

「従業員の健康は企業の財産になる」という健康経営の考え方が、近年、企業の経営戦略において重要視されています。少子高齢化が進み労働人口が減少する日本にとって、従業員が心身ともに健康で長く働き続けられる環境づくりは、企業価値を高めるうえで重要なポイントといえるでしょう。
この記事では、健康経営の概要や、健康経営を推進するメリット・デメリット、健康経営優良法人認定制度の内容を解説します。健康経営の具体的な実践方法もご紹介しているので、ぜひご一読ください。
健康経営とは
まずは、健康経営の概要や、健康経営が必要とされている理由を解説します。
健康経営の概要
健康経営とは、従業員などの健康管理を企業の成長に欠かせない経営戦略として捉え、戦略的に実践することを指します。アメリカの臨床心理学者ロバート・ローゼン博士が提唱した「個人の健康増進を図ることが企業の業績向上につながる」とするヘルシーカンパニーの概念に基づくものです。
この考えが企業経営者に幅広く受け入れられ、従業員の健康を経営的視点で考える健康経営の手法がビジネスに浸透するようになりました。
健康経営が必要とされている理由
経済産業省の資料によると、少子高齢化により今後100年間で日本の総人口は100年前の水準へと急激に減少していく可能性が指摘されています。
日本の人口は明治維新が起こった1868年には3,330万人、終戦を迎えた1945年には7,199万人、2010年には1億2,806万人と推移しました。しかし同資料によると、2030年には1億1,662万人、2050年には9,708万人、2100年には中位推計で4,959万人(低位推計で3,795万人)になると予測されています。
また近年は、労働力が減少し続けるなかで働く人々の高齢化が進んでいるだけでなく、がんや心疾患、脳血管疾患といった生活習慣病を患う方も増加している状況です。長時間労働による過労、パワハラ、職場の人間関係などにより、メンタルヘルスの不調を抱える方も少なくありません。
特に中小企業にとっては、一人の従業員が休職・退職するだけでも経営上の大きな痛手となり得ます。このような状況で企業が持続的に成長していくためには、現在働いている従業員に長く健康で働き続けてもらうことが重要です。
こうした理由により、従業員の健康を経営基盤とする健康経営の考え方が重視されてきているのです。
健康経営が企業にもたらす5つのメリット

ここからは、企業が健康経営に取り組むメリットを解説します。
1. 業績が伸びる可能性がある
帝国データバンクの調査によると、ROA(総資産経常利益率)・ROS(売上高営業利益率)ともに、2021年認定・2022年認定健康経営優良法人企業が認定なしの企業を上回る推移を見せました。
特に認定なしの中小企業の平均ROAは減少し続けている一方で、認定健康経営優良法人企業は横ばいで推移しています。ROSに関しても、認定なしの企業のみ減少しているのが実情です。
このデータからは、健康経営が利益率の向上に寄与する可能性があることを読み取れます。
出典:帝国データバンク|健康経営に関する企業の取り組み状況や効果に関する調査分析
2. 生産性が向上する
従業員が心身ともに健康な状態で業務に取り組めるようになると仕事のパフォーマンスが高まり、結果として生産性の向上につながります。
また、生産性の高い従業員は組織全体にも好影響を与え、企業の成長に寄与する点もメリットです。
3. 離職率が低下する
従業員の心身が健康であれば、病気や不調を抱えて休職・退職するリスクが減り、離職率も低下します。
実際、経済産業省の調査によると、健康経営優良法人認定企業は一般の企業よりも離職率が低い結果が出ています。具体的には、全国平均の離職率(2023年の参考数値)が12.1%なのに対し、健康経営優良法人2025に認定された企業の離職率は6.1%と約半分です。
また、健康経営優良法人の大企業部門の上位法人であるホワイト500(銘柄を除く)では離職率が4.8%、健康経営銘柄2025に選ばれている企業では離職率が3.5%とさらに低い水準となっています。
出典:経済産業省|これからの健康経営について(2025年4月)
4. 企業イメージが向上する
従業員が心身ともに健康で働きやすい環境を整えている企業は、社会的な評価が高まり企業イメージが向上するメリットもあります。結果として採用活動で多くの求職者が集まるようになり、優秀な人材の確保にもつながるでしょう。
また、企業のブランドイメージの向上は、顧客からの知名度向上にも寄与します。
5. 労働災害を予防できる
労働災害(労災)とは、従業員が業務中や通勤中にケガをしたり病気になったりすることを指します。業種別では製造業で最も労災の発生件数が多い傾向があります。例えば転倒、墜落・転落、無理な動作による事故が挙げられます。
労災は特に50歳以上の労働者によるものが全体の約半分を占めており、加齢による体力や身体機能の低下が一因と考えられています。そのため、健康経営に取り組んで従業員が心身ともに健康な状態で働ける環境を整備すれば、結果的に労災の予防にもつながるでしょう。
健康経営を推進する3つのデメリット

健康経営を推進するうえでは、いくつかのデメリットも考慮する必要があります。
1. 効果が見えにくい
健康経営の効果はすぐに数値として現れにくいため、投資効果を把握するのが難しい傾向です。
また、健康経営は中長期的な取り組みのため、従業員の健康に関する状況を定期的にヒアリングする必要もあります。こうした点から、健康経営を実践したいと思っても経営層からの理解が得られない場合もあるでしょう。
2. データの収集・管理コストがかかる
健康経営では従業員の健康データを収集・管理する手間やコストが発生し、従業員が多いほどその負担は大きくなります。
また、体調不良を訴える従業員に医師の面談をセッティングしたり、データの専門的な分析を専門家に依頼したりする場合、人件費がかさむ可能性があります。
3. 従業員の負担が増加する
健康経営を実施するためには、ストレスチェックやアンケートなど従業員の協力が必要です。なかにはアンケートの作成やセミナーの開催など、施策の企画・運営に携わる従業員も出てくるでしょう。
これらの取り組みは業務と別に行なうため、従業員にとっては負担になる可能性があります。健康経営を実施するためには、従業員に目的や理由をしっかりと伝え、理解と協力を得ることが重要です。
健康経営優良法人認定制度とは
健康経営優良法人認定制度の概要、認定を受けた企業が得られる称号について解説します。
健康経営優良法人認定制度
健康経営優良法人認定制度とは、優良な健康経営を実施している企業を認定する制度です。企業における健康経営を推進する目的で、2017年度から開始されました。規模の大きい企業を対象とした「大規模法人部門」、中小企業を対象とした「中小規模法人部門」の2つに分けられています。
健康経営優良法人に認定された企業は「健康経営優良法人」のロゴマークをホームページや名刺などで使えます。
認定申請料は大規模法人部門で1件につき8万円(税込8万8,000円)、中小規模法人部門で1件につき1万5,000円(税込1万6,500円)となっています。
「ホワイト500」「ブライト500」「ネクストブライト1000」制度
大規模法人部門の上位法人は「ホワイト500」、中小規模法人部門の上位500法人は「ブライト500」、上位501位~1,500位の法人は「ネクストブライト1000」に認定されます。これらの認定を受けると、健康経営優良法人のなかでも優れた企業であることをアピール可能です。
これらの上位法人に認定されるには、「従業員パフォーマンス指標および測定方法の開示」など、通常よりも多くの必須評価項目をクリアすることが求められます。
健康経営優良法人に認定される5つのメリット

健康経営優良法人に認定されると、企業はさまざまなメリットを享受できます。
1. 入札での加点対象になることがある
自治体が実施する公共工事の入札では、企業の社会的責任や持続可能性を厳しくチェックされる傾向です。
その点、健康経営優良法人の認定を受けていると社会的責任や持続可能性のある企業として高く評価され、入札時に加点評価の対象になることがあります。結果として案件を受注できる可能性が高まり、経営の安定や売上の向上につながる点は大きなメリットといえるでしょう。
2. 一部の補助金で加点対象になる
IT導入補助金など、一部の補助金制度では健康経営優良法人への認定が加点対象となっています。これにより補助金の採択率が上がるため、新たな事業への資金調達がしやすくなる点がメリットです。
3. 保険料の割引対象になることがある
健康経営優良法人に認定されると、保険会社から「従業員の健康管理にしっかりと取り組んでいる」と評価されて保険料の割引を受けられることがあります。
健康経営優良法人の認定を受けることは企業の財務上のメリットになるだけでなく、従業員の福利厚生の一環としても魅力であるといえます。
4. 融資金利の優遇対象になることがある
健康経営に取り組む企業はリスク管理ができていると評価され、金融機関から融資を受ける際に金利引き下げの優遇を受けられる場合があります。
融資金利が優遇されると資金調達コストを削減でき、経営の安定や投資の促進につながるため、特に中小企業にとっては財務上の大きなメリットになります。
5. 自治体などのインセンティブが受けられる
健康経営に取り組む企業は、自治体の公共工事の入札審査における加点などの恩恵を受けられるケースがあります。
詳細は自治体や金融機関により異なるため、以下で確認してください。
出典:日本経済新聞社|ACTION!健康経営 地域の取り組み
健康経営優良法人の認定要件

前述のように健康経営優良法人認定制度には大規模法人部門と中小規模法人部門の2つがありますが、それぞれ認定要件は異なります。令和7年度の認定要件は以下のとおりです。
大規模法人部門
大規模法人部門には以下の法人が該当します(「会社法上の会社等」または「士業法人」の場合)。
・卸売業:従業員数101人以上
・小売業:従業員数51人以上
・サービス業:従業員数101人以上
・製造業その他:従業員数301人以上
大規模法人部門の認定基準は「1.経営理念」「2.組織体制」「3.制度・施策実行」「4.評価・改善」「5.法令遵守・リスクマネジメント」の5つの大項目で構成されています。これらの大項目に、それぞれ細かな評価項目が設けられている点が特徴です。
評価項目には実施が必須のものと、規定の数をクリアしていることが条件になっている項目があります。
中小規模法人部門
中小規模法人部門には以下の法人が該当します(「会社法上の会社等」または「士業法人」の場合)。
・卸売業:「従業員数」1人以上100人以下、もしくは「資本金または出資金額」1億円以下
・小売業:「従業員数」1人以上50人以下、もしくは「資本金または出資金額」5,000万円以下
・サービス業:「従業員数」1人以上100人以下、もしくは「資本金または出資金額」5,000万円以下
・製造業その他:「従業員数」1人以上300人以下、もしくは「資本金または出資金額」3億円以下
中小規模法人部門の評価基準は「1.経営理念・方針」「2.組織体制」「3.制度・施策実行」「4.評価・改善」「5.法令遵守・リスクマネジメント」の5つの大項目で構成されています。
このうち、「1.経営理念・方針」「2.組織体制」「4.評価・改善」「5.法令遵守・リスクマネジメント」の認定基準の項目はすべてクリアする必要があります。ただし、「3.制度・施策実行」については定められた項目を満たしていることが条件です。
健康経営優良法人の認定までの流れ
健康経営優良法人に認定されるまでのプロセスを解説します。
大規模法人部門
大規模法人部門の認定までのプロセスは以下のとおりです。
1.「ACTION!健康経営」ポータルサイトより申請申込ページに移動する
2.従業員の健康に関する取り組みについての調査(健康経営度調査票)に回答する
3.認定委員会において審議が行なわれる
4.日本健康会議が認定する
中小規模法人部門
中小規模法人部門の認定までのプロセスは以下のようになっています。
1. 所属する健康保険組合の健康宣言事業に参加する(健康保険組合で健康宣言事業を実施していない場合は2.から始める)
2.「ACTION!健康経営」ポータルサイトより申請申込ページに移動する
3.「健康経営優良法人(中小規模法人部門)認定申請書」をダウンロードし、取り組み状況を記載してアップロードする
4.認定委員会において審議が行なわれる
5.日本健康会議が認定する
これからの人的資本経営と健康経営
2020年に経済産業省が「人材版伊藤レポート」を公表して以降、健康経営は人的資本の視点で推進されつつあります。ここからは、人的資本経営と健康経営の関係を解説します。
人的資本経営とは
人的資本経営とは、従業員一人ひとりの人材価値を最大限に引き出すことで、企業価値の向上につなげる経営手法です。人材への積極的な投資を通じて、企業全体の競争力や生産性を高めることを目的としています。
近年では企業の将来性を判断する指標として、人的資本に関する情報開示を求める動きが強まっています。例えば、2023年3月期決算から、一部の企業を対象に「男女間賃金格差」「女性管理職比率」「男性育休取得率」の情報開示が義務化されました。
人的資本経営と健康経営の関係
健康経営は先述のとおり、従業員の健康を管理し、労働環境や働き方の改革に取り組む経営手法で、人的資本経営の実践においても重要な概念です。
具体的には、人的資本経営が「企業価値の向上のために従業員価値を高める」ことを目指す一方で、健康経営は「従業員の健康を促進し個々の人材の価値を高める」ことを目的としています。つまり、人的資本経営を実践するためには健康経営が不可欠ということです。
最近では、健康経営の健康指標が人的資本の重要指標として注目を集めています。現状、健康指標の情報開示は義務化されていませんが、将来的には義務の対象となる可能性もあります。
そのため、今後は人的資本経営と健康経営を連動させて健康施策を講じることがより重要になっていくでしょう。
人的資本経営・健康経営を加速させるには多拠点型シェアオフィス「H¹T」がおすすめ
人的資本経営と健康経営を連動させた健康施策を推進する方法の一つとして、従業員の時間や場所にとらわれない柔軟な働き方を実現するオフィス戦略があります。
従業員が自分の状況に合わせて働き方を選べるようにすると、従業員の心身の健康を促進でき、エンゲージメントや組織全体の生産性、企業価値の向上を目指せます。
このような新しいオフィス戦略としておすすめなのが、多拠点型シェアオフィス「H¹T(エイチワンティー)」です。
「H¹T」は、企業の働き方改革の推進に役立つ多拠点型シェアオフィスです。提携店を含めて全国47都道府県に展開しており、在宅ワークだけでなく出張時にも気軽に利用できます。
初期費用は不要で、15分110円から利用できる手軽な料金設定も特徴です。スマートフォンのアプリを通じて簡単に予約・変更・キャンセルができるほか、スマートキーでの入退出や防犯カメラ、遠隔操作を防ぐGPS入室管理機能など、セキュリティ面も充実しています。
オンライン会議や採用面接、集中作業など多様なビジネスシーンで活用できるシェアオフィスです。
まとめ
健康経営とは、従業員の心身の健康管理を経営的な視点から戦略的に実施する取り組みです。少子高齢化により労働人口が減少し続ける日本では、従業員に長く健康で働いてもらうためにも健康経営がますます重要になっています。
健康経営には、従業員の離職率低下や生産性・企業イメージの向上といったメリットがあります。また、自治体や金融機関からのインセンティブを受けられる、労働災害の予防につながる点もメリットです。
しかし、効果が数字で把握しにくい、データの収集・管理にコストがかかる、従業員の負担が増加するといったデメリットがあるのも事実です。そのため、健康経営を推進するには事前に目的を従業員にしっかり伝え、理解してもらってから協力を仰ぐことが重要です。
なお、従業員の人材価値を引き出して企業価値を高める「人的資本経営」と、従業員の健康促進を重視する「健康経営」を連携させるには、時間や場所にとらわれない働き方を実現するオフィス戦略が有効です。
このような企業のオフィス戦略の一環として、多拠点型シェアオフィス「H¹T(エイチワンティー)」の活用をぜひご検討ください。